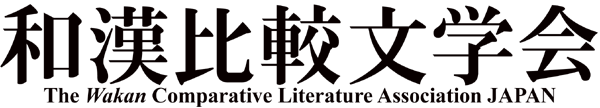
和漢比較文学会 大会発表題目一覧
| ■第1回大会 昭和58(1983)年 | 於 中央大学 |
|
10月14日 (研究発表) |
|
| ◎菊の賦詩歌の成立─本朝における古今集前夜までの菊の文学小史─ | 富山女子短期大学:本間洋一 |
| ◎平安朝漢文学者の言語感覚─神田本白氏新楽府を通して─ | 幾徳工業大学:津田潔 |
| ■第2回大会 昭和59(1984)年 | 於 中央大学 |
|
6月1日 (研究発表) |
|
| ◎和漢朗詠集の板本の本文をめぐって─和歌を中心に─ | 奈良女子大学(院):蔵中しのぶ |
| ◎『和漢朗詠集私注』の変貌─平安末期から室町期にかけての『和漢朗詠集私注』諸本の動向と関連して─ | 梅花女子大学:三木雅博 |
| ◎文曲星神白居易の伝の周辺 | 早稲田大学:柳瀬喜代志 |
| ◎和漢比較文学研究の一視点 | 熊本大学:金原理 |
| ■第3回大会 昭和59(1984)年 | 於 奈良女子大学 |
|
10月26日 (研究発表) |
|
| ◎『江都督納言願文集』について | 中央大学(院):細田季男 |
| ◎『槐記』に見える家凞公の読書生活 | 奈良女子大学:松尾肇子 |
| ◎驪姫外伝─中世史記の世界から─ | 関西大学:黒田彰 |
| ◎「題しらず」の「題」という語について | 早稲田大学:吉川栄治 |
| ◎平安漢詩文の縁語的表現について | 福岡教育大学:工藤重矩 |
| ◎中国と日本の漢詩をめぐって─江戸時代の漢詩の風景における夢と現実─ | 獨協大学:大矢マルグリット |
| ◎李暹注『千字文』について | 大阪大学:東野治之 |
| ■第4回大会 昭和60(1985)年 | 於 早稲田大学 |
|
10月18日 (研究発表) |
|
| ◎『助字辯略』と『詩語解』 | 奈良女子大学(院):坂井裕子 |
| ◎院政前期の宗教政策と大江匡房の創作活動 | 早稲田高等学院:吉原浩人 |
| ◎『新撰朗詠集』の成立 | 慶應義塾大学(院):佐藤道生 |
| ◎『三教指帰注』所引『文選』考 | 広島女子大学:山崎誠 |
| ◎仏伝文学の中国的展開と日本的展開について | 愛知学院大学:黒部通善 |
| ■第5回大会 昭和61(1986)年 | 於 仏教大学 |
|
10月24日 (研究発表) |
|
| ◎教訓抄引書小考 | 中央大学(院):宮崎和廣 |
| ◎白氏六帖について | 広島女子大学:山崎誠 |
| ◎貞慶上人の講式をめぐって | 大正大学(院):浅野祥子 |
| ◎『長谷雄草紙考』─草子と朗詠集─ | 愛知県立大学:黒田彰 |
| ◎敦煌文献と上代文学 | 大阪大学:東野治之 |
|
(講演) |
|
| 極東文学史上における人麿の位置 | 大阪大学:黒川洋一 |
| ■第6回大会 昭和62(1987)年 | 於 大正大学 |
|
11月14日 (研究発表) |
|
| ◎張飛と源為朝 | 法政大学:呉念聖 |
| ◎平基親撰『往生要集外典鈔』考 | 国文学研究資料館:山崎誠 |
|
(講演) |
|
| ◎漢文訓読と古辞書の和訓 | 中央大学:築島裕 |
| 11月15日 (研究発表) |
|
| ◎『蒙求』型類書の世界─異種『蒙求』書目の紹介と検討─ | 木所工業高校:相田満 |
| ◎『文鳳抄』の諸問題─編纂素材を中心に─ | 富山短期大学:本間洋一 |
| ◎白居易の病状診断 | 日本学術振興会奨励研究員:丹羽博之 |
| ◎平安朝における官職唐名の文学的側面 | 福岡教育大学:工藤重矩 |
| ■第7回大会 昭和63(1988)年 | 於 名古屋女子大学 |
|
11月12日 (研究発表) |
|
| ◎源能有五十賀屏風画詩について | 同志社大学(院):谷口孝介 |
| ◎和歌序に関する一考察 | 宮崎女子短期大学:原田真理 |
|
(シンポジウム) |
|
| ◎和漢比較文学の分野と方法─古代文学をめぐって─ |
|
| 司会 | 奈良女子大学:新井栄蔵 |
| 講師 | 中京大学:小沢正夫 |
| 講師 | 大阪大学:東野治之 |
| 講師 | 成城大学:杤尾武 |
| 講師 | 名古屋女子大学:八木毅 |
|
11月13日 (研究発表) |
|
| ◎教訓抄の撰述資料─楽記を中心に─ | 中央大学(院):宮崎和廣 |
| ◎『平治物語』の─変容和歌と漢詩句を中心にして─ | 中京大学:大島龍彦 |
| ◎都市へのまなざし─『池亭記』異論─ | 桃山学院大学:深沢徹 |
| ◎『本朝無題詩』伝本考 | 慶應義塾大学:佐藤道生 |
| ◎和歌における「霞」の表現─漢詩文との関わりをめぐって─ | 岐阜教育大学:安田徳子 |
| ■第8回大会 平成元(1989)年 | 於 早稲田大学 |
|
11月17日 (研究発表) |
|
| ◎志貴皇子と長皇子の交遊 | 慶應義塾大学(院):池田三枝子 |
| ◎『筥崎宮記』成立の背景 | 早稲田大学:吉原浩人 |
|
(講演) |
|
| ◎神道書と仏道二教 | 早稲田大学教授:菅原信海 |
| ◎漢籍旧鈔本に関する諸問題 | 慶應義塾大学名誉教授・東横学園女子短期大学教授:太田次男 |
|
11月18日 (研究発表) |
|
| ◎勅撰三集の編纂方針について─官人の位署と序列─ | 浦和市立高校:阿部芳夫 |
| ◎『性霊集』と白居易の閑適詩 | 駒沢短期大学:大塚英子 |
| ◎王朝和歌と漢詩文─その表現をめぐっての諸問題─ | 富山女子短期大学:本間洋一 |
| ◎張庭芳撰〈李嶠百二十詠詩注〉考─漢籍の講誦における異本化問題一斑─ |
復旦大学:胡志昂 大阪大学:後藤昭雄 |
| ■第9回大会 平成2(1990)年 | 於 梅光女学院大学 |
|
11月16日 (講演) |
|
| ◎野村篁園の「集唐詩」について | 明治大学教授:徳田武 |
| ◎白楽天の詩賦と王朝の詩賦 | 九州大学名誉教授・久留米大学教授:岡村繁 |
|
11月17日 (研究発表) |
|
| ◎山部赤人の対句表現 | 早稲田大学(院):太田豊明 |
| ◎大津皇子「臨終」詩群の解釈 | 甲南高校:濱政博司 |
| ◎日本文学にみられる王子猷像 | 甲南女子大学(院):田中幹子 |
| ◎白詩語「撥簾」受容考─菅原道真を中心に─ | 神戸大学(院):中島和歌子 |
| ◎最古注蒙求の検証作業の問題点 | 無窮会特別研究員:相田満 |
| ◎大道直如髪─江戸戯作者の唐詩受容─ | 小倉女子商業高校:山口公和 |
| ■第10回大会 平成3(1991)年 | 於 相模女子大学 |
|
11月16日 (研究発表) |
|
| ◎漢語小考─唐詩の注釈から─ | 成城大学(院):妹尾昌典 |
| ◎愕拯・桑間濮上之音─大東急記念文庫蔵二十巻本『和名類聚抄』音楽部「箜篌」の条の背景について─ | 関西外国語短期大学:米山敬子 |
|
(シンポジウム) |
|
|
王朝漢詩選集の美意識 |
|
| 司会 | 信州大学:渡辺秀夫 |
| 講師 | 同志社女子大学:本間洋一 |
| 講師 | 梅花女子大学:三木雅博 |
| 講師 | 金沢女子大学:柳澤良一 |
|
11月17日 (研究発表) |
|
| ◎我国古代文献における喪葬儀礼について | 早稲田大学:及川智早 |
| ◎菅原道真論序説─「菊」の表現を通して─ | 聖心女子大学:佐藤信一 |
| ◎和漢にみる「退避・逃走」表現の相異「史記」と「太平記」 | 札幌市立藻岩高校:中嶋みゆき |
| ◎『竹林抄』古注釈書に見える漢籍由来の付合について | 大阪大学(院):中本大 |
| ◎蠣崎波響の叔父 | 金城学院大学:高橋博巳 |
| ◎国学者・漢学者の古代和歌論 | 小沢正夫 |
| ■第11回大会 平成4(1992)年 | 於 北海学園大学 |
|
9月26日 (研究発表) |
|
| ◎西府の大江匡房 | 慶應義塾大学:佐藤道生 |
|
(講演) |
|
| ◎平安朝文学にみえる囲碁 | 中央大学教授:大曽根章介 |
| ◎国文学研究におけるもう一つの視点 | 北海道教育大学名誉教授:小泉弘 |
|
9月27日 (研究発表) |
|
| ◎『妙法蓮華経釈文』における「玄奘云」「不空云」について |
金城学院大学:西原一幸 愛知学院大学:河野敏宏 |
| ◎漢語「青~」の影響を受けて成立した古代日本の「あを」 | 早稲田大学(院):丹羽晃子 |
| ◎和漢朗詠集古写本の詩題注について | 甲南女子大学(院):田中幹子 |
| ◎太平記における漢籍について─長恨歌の場合を通して─ | 札幌市立藻岩高校:中嶋みゆき |
| ◎慈円『文集百首』の考察 | 広島女子大学:石川一 |
| ◎元白・劉白の文学と源氏物語 | 甲南大学:新間一美 |
| 9月28日 (シンポジウム) |
|
| 万葉・古今・新古今と漢文学─和漢比較文学の現在─ |
|
| 司会 | 早稲田大学:上野理 |
| 講師 | 長野工業高等専門学校:曽田友紀子 |
| 講師 | 大手前女子大学:丹羽博之 |
| 講師 | 中央大学:長崎健 |
| ■第12回大会 平成5(1993)年 | 於 徳島文理大学香川校 |
|
11月13日 (公開講演) |
|
| ◎竹取物語の定位 | 徳島文理大学教授:奥津春雄 |
| ◎失われた唐渡り書─張文成『朝野僉載』の周辺─ | 神戸外国語大学教授:蔵中進 |
| 11月14日 (研究発表) |
|
| ◎大津皇子の詩─「春苑言宴」を中心に─ | 早稲田大学(院):井実充史 |
| ◎「向南山」考─万葉集百六十一番歌試解─ | 同志社大学:谷口孝介 |
| ◎『菅家文草』巻四所載の詩「江上晩秋」の解釈をめぐって─菅原道真の賦「秋湖賦」との関わり─ | 有明高専:焼山廣志 |
| ◎大江匡衡と菅原文時 | 鹿児島県立短期大学:木戸裕子 |
| ◎中国故事の古層と新層─『類林』系類書と『蒙求をめぐる問題について─ | 国文学研究資料館:相田満 |
| ◎竹から生まれた篁 | 国文学研究資料館:小峯和明 |
| ■第13回大会 平成6(1994)年 | 於 中京大学 |
|
11月19日 (公開講演) |
|
| ◎日本文学と漢民族の民間思想 | 駒澤大学教授:中村璋八 |
| ◎漢語と和語と─和漢比較文学研究への期待─ | 国文学研究資料館名誉教授:新井栄蔵 |
|
(研究発表) |
|
| ◎上代和歌における「叙景歌」の成立と漢詩文─宴席における〈景〉の機能─ | 早稲田大学(非):高松寿夫 |
| ◎『徒然草』第二百二十七段攷─太秦の善観房と云ふ僧、節博士を定めて声明になせり─ | 立命館大学:村上美登志 |
|
11月20日 (研究発表) |
|
| ◎日本古代における異境─うつほ物語・俊蔭巻を中心に─ | 神戸大学:項青 |
| ◎地蔵説話における〈蘇生〉の意味するもの─今昔物語集・地蔵菩薩霊験記を中心として─ | 梅光女学院大学(院):好村友江 |
| ◎『愚迷発心集直談』の意義 | 大正大学総合仏教研究所研究員:浅野祥子 |
| ◎近世初期の題画文学 | 茨城大学:鈴木健一 |
| ◎国学と漢籍注解─足羽敬明 五国史故事考の方法─ | 札幌南高校:細田季男 |
| ■第14回大会 平成7(1995)年 | 於 神戸大学 |
|
11月25日(研究発表) |
|
| ◎『池上篇』から『池亭記』『方丈記』まで─その思想的特徴をめぐって─ | 北京外国語大学:雋雪艶 |
|
(公開シンポジウム) |
|
| 白詩文集と平安文学 |
|
|
基調報告 |
|
| ◎中国人の立場より見た白詩文集と平安文学 | 台湾大学名誉教授:林文月 |
|
報告 |
|
| ◎中唐以後の文学と白居易 | 三重大学:西村富美子 |
| ◎白居易の詩人意識と『菅家文草』『古今序』─詩魔・詩仙・和歌ノ仙─ | 甲南大学:新間一美 |
| ◎定家と白詩 | 香川大学:佐藤恒雄 |
|
11月26日(研究発表) |
|
| ◎鵲について─平安詩歌を中心に─ | 日本学術振興会特別研究員:田中幹子 |
| ◎「鉄枴仙」像の受容と定着 | 大阪大学:中本大 |
| ◎祇園南海の詩作と推敲─青春期を中心として─ | 立花学園高校:杉下元明 |
| ◎龍草廬グループの展開とその様相 | 九州大谷短期大学:安保博史 |
| ◎湘夢遺稿にみえる中国女流詩人の影 | 無窮会東洋文化特別研究員:小林徹行 |
| ◎大兄匡房の嘉承二年「賀朔旦冬至表」─異例の事態に重なった草稿の混入─ | 慶應義塾大学:佐藤道生 |
| ■第15回大会 平成8年(1996)年 | 於 金沢学院大学 |
|
9月28日(公開講演) |
|
| ◎朝鮮印刷文化と日本 | 富山大学:藤本幸夫 |
| ◎鷲の建国神話と鷹の万葉歌 | 新潟大学:山口博 |
|
(研究発表) |
|
| ◎和漢朗詠集「閏三月」部に見られる公任の編纂意識について | 日本学術振興会特別研究員:田中幹子 |
| ◎「老鶯」と「鶯の老い声」 | 神戸女子大学:北山円正 |
|
9月29日(研究発表) |
|
| ◎『古今集』における白詩享受の一側面─黒髪を通して─ | 神戸薬科大学(非):岩井宏子 |
| ◎『紫式部集』の漢詩文受容─「折りて見ば」の歌の寓意について─ | 京都大学(院):山本淳子 |
| ◎藤壺物語の構想と武則天の関係試論 | 甲南女子大学(院):郭潔梅 |
| ◎申文の論理─『本朝文粋』を中心として─ | 群馬工業高等専門学校:小野泰央 |
| ◎十四巻本『三国因縁地蔵菩薩霊験記』における中国の仏教説話の受容─「教偈救苦事」四ノ三「王氏得霊験事」五ノ六を中心に─ | 筑紫女学園大学:好村友江 |
| ◎『史館茗話』考─その説話の典拠と本書の影響をめぐって─ | 同志社大学:本間洋一 |
| ■第16回大会 平成9(1997)年 | 於 大阪大学 |
|
10月25日(公開講演) |
|
| ◎敦煌本百歳篇と国文学について | 成城大学:杤尾武 |
| ◎待ち遠しかった講義─神田喜一郎先生のこと─ | 大阪府文化財保護審議会委員:水田紀久 |
|
10月26日(研究発表) |
|
| ◎『文鏡秘府論』の撰述事情 | 熊本大学(院):大石有克 |
| ◎「この君」と呼ばれる幼児薫─竹の異名「此君」を典拠として─ | 同志社大学(院):桑原もと子 |
| ◎『源氏物語』と北宋白話の関係試論 | 同志社大学:郭潔梅 |
| ◎『本朝文粋』巻七所載「省試詩論」について─藤原明衡「犯鶴膝病預及第申文」との関わり─ | 早稲田大学(院):濱田寛 |
| ◎中世法家の秘伝『職原抄』『御成敗式目』注釈から | 国文学研究資料館:相田満 |
| ◎漁者樵者の系譜─蕪村から竹田へ─ | 金城学院大学:高橋博巳 |
| ■第17回大会 平成10(1998)年 | 於 福岡女子大学 |
| 10月24日(公開講演 日本学術協力財団との共催) |
|
| ◎中日間のブック・ロード─平安時代の書籍交流─ | 杭州大学日本文化研究所所長:王勇 |
| ◎近世における李卓吾受用─特に松陰以前─ | 九州大学文学部教授:中野三敏 |
| 10月25日(研究発表) |
|
| ◎神武記の「乗亀甲為釣乍打羽擧来人」について | 京都大学(院研修員):王小林 |
| ◎『源氏物語』胡蝶巻と『紫式部日記』─新楽府受容を媒介とした作家論的試み─ | 早稲田大学(院):岡部明日香 |
| ◎藤原俊成を巡る和歌と漢詩文の位相 | 早稲田大学(院):加畠吉春 |
| ◎地蔵説話の救済の様相─十四巻本『三国因縁地蔵菩薩霊験記』に至るまで─ | 筑紫女学園大学(非):好村友江 |
| ◎中国禅文学より見た「五山文学」の成立 | 福岡国際大学:兪慰慈 |
| ◎館柳湾の晩唐詩受容─皮日休・陸亀蒙の摂取例を中心に─ | 相愛女子短期大学(非):鷲原知良 |
| ◎中国へ伝えられた日本人の著作─淡海三船『大乗起信論注』─ | 大阪大学:後藤昭雄 |
| ■第18回大会 平成11(1999)年 | 於 早稲田大学 |
|
10月9日(公開講演) |
|
| ◎『文集抄』について | 大阪大学教授:後藤昭雄 |
| ◎日中比較詩学の可能性─詩的リズムの対比を中心に─ | 早稲田大学教授:松浦友久 |
| ◎カナの西伝と和歌の漢訳 | 北京大学比較文学文化研究所長:厳紹璗 |
|
10月10日(研究発表) |
|
| ◎藤原定家の和歌における対句的発想とその表現 | ノートルダム清心女子大学(院):見尾久美恵 |
| ◎庭園をめぐる思想─鵞峰・三竹の「独楽園記」受容を中心として─ | 早稲田大学(院):伊藤善隆 |
| ◎蘇詩研究における『四河入海』の意義 | 中央大学:池沢滋子 |
| ◎嵯峨朝詩人と詩律学 | 東京外語大学(院):黄少光 |
| ◎奈良朝漢詩文の人的ネットワーク─大安寺文化圏と藤原仲麻呂家─ | 大東文化大学:蔵中しのぶ |
| ◎『河海抄』の作られ方─『職原抄』引用から見える諸問題を中心に─ | 国文学研究資料館:相田満 |
| ■第19回大会 平成12年(2000年) | 於 信州大学 |
| 9月23日(公開シンポジウム) |
|
| 平安漢文世界の継承と変容―教訓・幼学・唱導― |
|
| 司会 | 東京大学助教授:藤原克己 |
| パネリスト | 山形大学教授:菊地仁 |
| パネリスト | 立教大学教授:小峯和明 |
| パネリスト | 梅花女子大学教授:三木雅博 |
|
9月24日(研究発表) |
|
| ◎風流と遊び ―踏歌と関連して― | 東京大学(院):李宇玲 |
| ◎「勅撰三集」における重陽節賜宴詩賦の展開 | 福島大学:井実充史 |
| ◎『菅家文草・菅家後集』『田氏家集』と中国の詩律学―貞観・延喜期の日本漢詩に見られる近体七言詩の規範意識― | 東京外国語大学(院):黄少光 |
| ◎『倭名類聚抄』所引『兼名苑』について | 神戸学院大学(院):林忠鵬 |
| ◎東大寺図書館蔵『遁世述懐抄』について | 大阪大学(院):仁木夏実 |
| ◎望郷 ―一茶と漢文学― | 東京家政学院大学(非): 杉下元明 |
|
9月25日(実地踏査) |
|
| A 日本民俗資料館、旧開智学校、木下尚江記念館、安曇野ちひろ美術館 |
|
| B 儀象堂、諏訪湖博物館、赤彦記念館、諏訪市博物館 |
|
| ■第20回大会 平成13年(2001年) | 於 相模女子大学 |
|
9月22日(公開シンポジウム) |
|
| 古代文学における和漢の説話―儒教・仏教・道教― |
|
| 司会・コーディネーター | 早稲田大学助教授:吉原浩人 |
| パネリスト | 駒沢大学教授:田中徳定 |
| パネリスト | 東京都立晴海総合高校教諭:河野貴美子 |
| パネリスト | 東京成徳大学助教授:増尾伸一郎 |
|
9月23日(研究発表) |
|
| ◎日本における漢文体の誄 | 名古屋大学(院):井上和歌子 |
| ◎『文華秀麗集』「春怨考」 | 函館大学付属柏陵高校:半谷芳文 |
| ◎謡曲における漢詩文の享受―古作『昭君』を中心に― | 安田女子大学(院):三多田文恵 |
| ◎日本近世文学における李白受容の一斑 | 二松学舎大学(院):熊慧蘇 |
| ◎大江匡衡と老子 | 鹿児島県立短期大学:木戸裕子 |
| ◎『和漢朗詠集』注釈の序部・開題部における「和漢」 | 国文学研究資料館:相田満 |
| ◎『伊勢物語』第二十四段と孟姜女故事 | 法政大学(非) :中野方子 |
| ◎『うつほ物語』「俊蔭」巻の仏教受容―捨身供養譚(「捨身飼虎」「施身聞偈」)を中心に― | 聖徳大学短期大学部:正道寺康子 |
|
9月24日(実地踏査) |
|
| 無窮会図書館貴重図書の参観 |
|
|
■「日中比較文学国際学術検討会」 (中日比較文学学会との合同) |
中華人民共和国 広州市 中山大学 |
| テーマ:「新世紀の日中文学関係―その回顧と展望」 |
|
| 会場校責任者:中山大学日語科副主任佟君 |
|
|
事務局: 和漢比較文学会 代表理事 矢作武(相模女子大学) 中日比較文学学会 会長 厳紹璗(北京大学) |
|
| 12月7日(金)到着・受付 |
|
| 12月8日(土)午前:開幕式。基調講演(日・中各一人)、午後:発表会 |
|
| 12月9日(日)発表会 |
|
| 12月10日(月)広州市内近辺の学術見学 |
|
| ■第21回大会 平成14年(2002年) | 於 太宰府天満宮 |
|
9月28日(研究発表) |
|
| ◎良岑安世「奉二和河陽十詠一五夜月」の一側面―心情の表現の進化― | 大阪市立大学(院):豊野宙麿 |
| ◎『経国集』試帖詩考 | 函館大学付属柏稜高校:半谷芳文 |
| ◎商人と釣翁―范蠡伝の変容― | 慶応義塾大学(院):山田尚子 |
| ◎近世国学思想の一側面―『三大考』と宋学の関連をめぐって― | 香港城市大学:王小林 |
| ◎田能村竹田の漢詩文にみる煎茶 | 神戸大学(院):舩阪富美子 |
|
9月29日(研究発表) |
|
| ◎『菅家文草』の献上―その編纂意識・目的・そして『菅家後集』へ― | 成蹊大学(院):前田明史 |
| ◎菅原道真における中国文学の受容―「叙意一百韻」を中心に― | 福岡国際大学:兪慰慈 |
| ◎李嶠百詠の性格・評価と変容 | 埼玉学園大学:胡志昂 |
| ◎詩序の破題―日本漢学史上の菅原文時― | 慶応義塾大学:佐藤道生 |
|
(公開シンポジウム)菅原道真の文学世界 |
(司会)東京大学:藤原克己 |
| 詩臣道真の「言志」 | (パネリスト)奈良大学:滝川幸司 |
| 詩序を拓くもの | (パネリスト)筑波大学:谷口孝介 |
| 道真詩の表現と中国語 | (パネリスト)九州大学:静永健 |
|
9月30日(実地踏査) |
|
| A 太宰府政庁跡、戒壇院、観世音寺、天満宮歴史館、宝物殿、光明禅寺、九州歴史博物館 |
|
| B 咸宜園、広瀬資料館、桂林荘跡 |
|
| ■第22回大会 平成15年(2002年) | 於 法政大学 |
|
9月20日(公開講演会) |
|
| 黄遵憲『日本国志』の出典について | 浙江大学日本文化研究所副所長・教授:王宝平(二松学舎大学大学院特任教授) |
| 敦煌文献学の現在 | 北海道大学大学院教授:石塚晴通 |
|
9月21日(研究発表) |
|
| ◎勅撰三集時代における征東詩の成立背景について | 大阪大学(院):山谷紀子 |
| ◎島田忠臣の納涼詩における白詩受容をめぐって | 甲南大学(非):岩井宏子 |
| ◎策問の史的展開 | 慶応義塾大学:佐藤道生 |
| ◎女は春をあはれぶ―若菜巻の春と『詩経』引用― | 相模女子大学:後藤幸良 |
| ◎世阿弥と漢籍 | 帝塚山大学:王冬蘭 |
| ◎雪中庵社中編『唐詩三物』について―近世中期『唐詩選』流行の一側面― | 明治大学:池澤一郎 |
|
■第23回大会 平成16年(2004年)
共催:九州大学21世紀COEプログラム |
於 九州大学 |
|
11月13日(公開シンポジウム「東アジアの中の白楽天」) |
|
|
第一部「平安文学と白楽天」 |
(司会)筑波大学:谷口孝介 |
| 源氏物語と白氏文集 | 台湾大学:陳明姿 |
| 平安後期文人たちの白詩受容 | 清華大学:雋雪艶 |
| 日本人の心の歴史と白氏文集 | 東京大学:藤原克己 |
|
第二部「東アジアの古典としての白楽天」 |
(司会)九州大学:静永健 |
| 高麗朝の詩人李奎報における白詩受容 | 成均館大学校:金卿東 |
| 初めての『白居易詩集校注』編撰事業 | 清華大学:謝思煒 |
| 戦後日本における白居易研究 | 岡山大学:下定雅弘 |
|
11月14日(研究発表) |
|
| ◎「方丈」考 | 鹿児島大学(非):富原カンナ |
| ◎夭折の嘆き―『土左日記』と建安詩文との関わり― | 大阪市立大学(院):江藤高志 |
| ◎『日蔵夢記』の年紀記事攷―道賢銘経筒銘文との比較考察― | 菊地真 |
| ◎詠物詩から句題詩へ | 北京日本学研究センター博士後期課程:蒋義喬 |
| ◎江戸後期の関西詩壇と神韻説―頼山陽を中心に― | 台湾大学:朱秋而 |
| ◎明治漢詩と王士禛 | 京都大学大学院文学研究科COE研究員:福井辰彦 |
| ◎「職は只太子賓客」―大江匡衡と白楽天― | 鹿児島県立短期大学:木戸裕子 |
| ◎菅原道真「九月十日」詩の解釈について | 早稲田大学:堀誠 |
| ■第24回大会 平成17年(2005年) | 於 京都女子大学 |
|
10月1日(公開講演会) |
|
| 定家と漢詩 | 元ノートルダム清心女子大学大学院教授:赤羽淑 |
| 空海と平安朝初期の漢詩 | 京都大学名誉教授:興膳宏 |
|
10月2日(研究発表) |
|
| ◎鴻臚館の光る君―高麗人の予言とのかかわりから― | 國學院大学(院): 笹川勲 |
| ◎和歌と漢詩における共感覚表現について | 名古屋大学(院) :趙青 |
| ◎秋成と『論衡』 | 京都女子大学(院) :李婷 |
| ◎菅原道真と古今和歌集―「鶯花」をめぐって― | 大阪大学(院) :高兵兵 |
| ◎破題の行方―朗詠註展開の一側面― | 慶應義塾中等部(非) :山田尚子 |
| ◎『和漢朗詠集』、幼学書への道 | 慶應義塾大学:佐藤道生 |
| ◎円宗寺五大堂供養考 | 国文学研究資料館:山崎誠 |
| ■第25回大会 平成18年(2006年) | 於 同志社女子大学 |
|
9月24日(公開講演会) |
|
| 『招提寺流記』初探―平安前期漢文作品の一例― | 奈良大学教授:東野治之 |
| 東アジアの角筆文献 その交流の軌跡を辿る | 徳島文理大学大学院教授・広島大学名誉教授:小林芳規 |
|
9月25日(研究発表) |
|
| 中院通勝「句題五十首」について―四字句題と四字結題― | 大阪大学(院):山田理恵 |
| 『賦光源氏物語詩』について | 群馬工業高等専門学校:小野泰央 |
| 和刻本漢籍の来源 | 慶應義塾大学附属研究所斯道文庫:住吉朋彦 |
| 『古今集』業平の贈答歌と戯作詩 | 中央大学(非):中野方子 |
| 『江都督納言願文集』巻五「右大弁為房母逆修」について | 埼玉学園大学:山部和喜 |
| 白氏文集と色葉字類抄 | 新潟大学:舩城俊太郎 |
| 『蜻蛉日記』と漢文学 | 京都大学:大谷雅夫 |
| ■第26回大会 平成19年(2007年) | 於 慶應義塾大学 |
|
9月29日(公開講演会) |
|
| 唐詩の新資料・朝鮮本『夾注名賢十抄詩』をめぐって―『千載佳句』との関連性― | 立命館大学教授:芳村弘道 |
| 東アジア比較文学の構想 | 京都大学人文科学研究所教授・所長:金文京 |
|
9月30日(研究発表) |
|
| 『方丈記』に見られる中国隠逸思想の変容 | 名古屋大学(院):田云明 |
| 題壁詩と和歌 | 早稲田大学高等学院(非):加畠吉春 |
| 三条西家旧蔵『経国集』紙背文書について | 鶴見大学:堀川貴司 |
| 『日本三代実録』の「凡例」―天文記事を中心に― | 筑波大学:谷口孝介 |
| 西本願寺本三十六人集「躬恒集」の漢詩を巡って | 大手前大学:丹羽博之 |
| 源氏物語の長編構想と仏伝 | 京都女子大学:新間一美 |
| ■第27回大会 平成20年(2008年) | 於 東北大学 |
|
9月27日(公開講演会) |
|
| 源氏物語と尚書―注釈史における儒教的言説と物語の方法― | 明治大学教授:日向一雅 |
| 善書からみる明清小説と江戸小説 | 東北大学名誉教授:小川陽一 |
|
9月28日(研究発表) |
|
| 廣瀬淡窓の李白への挑戦―「月下独酌」論― | 早稲田大学(院):小財陽平 |
| 江戸時代における『五雑組』の受容―上田秋成を中心に― | 京都女子大学(研):李婷 |
| 六如上人の宋詩受容―蛙と雨の描写を中心に― | 長崎大学:中島貴奈 |
| 「儒門の領袖」たらんとする道眞―『菅家文草』四十二番詩を読む― | 國學院大学(兼):谷本玲大 |
| 句題詩と省試詩 | 慶應義塾大学:佐藤道生 |
| 『全経大意』について | 成城大学:後藤昭雄 |
| ■第28回大会 平成21年(2009年) | 於 國學院大学 |
|
9月26日(公開シンポジウム) |
司会 神戸女子大学:北山円正 |
| 「唐代伝奇と平安朝物語」 パネリスト 「『遊仙窟』文化圏」構想は可能か―「かいまみ」と「女歌」― | 関西大学:山本登朗 |
| 漢文伝と唐代伝奇・物語―『続浦嶋子伝記』をめぐって | 信州大学:渡辺秀夫 |
| 伝奇と物語の美意識―〈文化ダイナミズム〉から見た中唐と平安朝の文学 | 愛媛大学:諸田龍美 |
| 源氏物語と唐代伝奇―基層としての遊仙窟 | 京都女子大学:新間一美 |
| 9月27日(研究発表) |
|
| 菅原道真詩における流水対 | 東京外国語大学(院):顧姍姍 |
| 『更級日記』と漢文学についての一試論―景物描写を中心に― | 京都大学(院):張稜 |
| 平安朝七言排律詩の盛行について | 函館大学付属柏稜高校:半谷芳文 |
| 宋詩の活用―「有難や雪をかほらす南谷」における薫風の技法 | 神戸大学(院):黄佳慧 |
| 『本朝続文粋』の勧学会詩序をめぐって | 早稲田大学:吉原浩人 |
| 三巻本色葉字類抄の割注部分に見いだされる白氏文集の語句について | 新潟大学:舩城俊太郎 |
| ■第29回大会 平成22年(2010年) | 於 信州大学 |
| 9月2日(公開講演会) |
|
| 松代藩六代藩主真田幸弘の文芸―漢詩・和歌・俳諧― | 清泉女学院大学教授:玉城司 |
| 和漢比較文学研究の射程―〈『源氏物語』と『後漢書』清河王慶伝〉再論― | 和洋女子大学教授:仁平道明 |
| 9月3日(研究発表) |
|
|
「年内立春詠」の和漢比較的研究 |
筑波大学(院):隋源遠 |
|
「暗香」考―「夜の梅」のイメージを中心に― |
創価大学(院):韓雯 |
|
三宅嘯山の『唐詩選』受容 |
明治大学(非):小財陽平 |
|
林家の隠逸思想と其角の市隠 |
早稲田大学(院):李國寧 |
|
水府明徳会蔵「詩集」について |
明石工業高等専門学校:仁木夏実 |
|
『王沢不渇鈔』における句題詩序の構成について |
熊本県立大学(非) :山田尚子 |
|
〈忠と孝との鬩(せめ)ぎ合い〉と中国孝子譚―『経国集』対策文から平家・近松へ― |
梅花女子大学:三木雅博 |
| ■第30回大会 平成23年(2011年) | 於 筑波大学 |
| 9月24日(研究発表) |
|
|
丈山の杜甫受容―「拙」をキーワードとして― |
湘北短期大学:伊藤善隆 |
|
蘐園学派における「不朽」の意義―服部南郭を中心として― |
東北大学(院):吉川裕 |
|
六如・棕隠の「わがともがら」意識について―宋詩との関わりを中心に― |
長崎大学:中島貴奈 |
|
大窪詩佛と詠物詩 |
早稲田大学(院):張淘 |
|
齋藤竹堂の『村居三十律』と 「山居」「江居」の「三十律」 |
茨城大学:堀口育男 |
|
和刻本『事文類聚』考―その本文と訓点について― |
慶應義塾大学:住吉朋彦 |
|
9月25日(研究発表) |
|
|
幸田露伴「共命鳥」考 |
筑波大学(院):王菁潔 |
|
『宿直文』巻四「維明和尚北野に伴作に遇ふ談」における三宅嘯山の創作手法 |
早稲田大学(院):河村公康 |
|
李学逵「草梁倭館詞」について―十九世紀朝鮮実学者の記した倭館・日本― |
大阪大学:合山林太郎 |
|
書儀・尺牘表現の受容―平安初期漢文書簡の表現を中心に― |
信州大学:西 一夫 |
|
9月25日(公開シンポジウム) |
|
| パネリスト | 成城大学教授:後藤昭雄 |
| パネリスト | 京都女子大学教授:新間一美 |
| 司会・パネリスト | 慶應義塾大学教授:堀川貴司 |
| パネリスト |
早稲田大学教授:池澤一郎 |
|
パネリスト |
立命館大学講師:福井辰彦 |
| ■第31回大会 平成24年(2012年) |
於 同志社女子大学 |
| 9月29日(公開講演会) |
|
|
江戸の杜詩学―葛西因是の「深読み」をめぐって― |
早稲田大学教授:池澤一郎 |
|
杜甫の〈越えて行く言葉〉―子規の眼― |
名古屋大学教授:加藤国安 |
|
9月30日(研究発表) |
|
|
石川雅望読本『近江縣物語』の方法 |
早稲田大学(院):任清梅 |
|
市河寛斎の唐五言古詩―『談唐詩選』を中心として― |
名古屋大学(院):金明蘭 |
|
橋の記憶―随心院蔵『慶長五年修法記』収載「多摩川六郷橋祝文」をめぐって― |
国文学研究資料館:相田満 |
|
世阿弥本『弱法師』の一典拠―弱法師の見たもの― |
京都大学(非):中村健史 |
|
後土御門天皇の内々和漢聯句御会懐紙について |
天理大学:小山順子 |
|
大江匡衡と元白唱和 |
鹿児島県立短期大学:木戸裕子 |
|
『朝野群載』巻十三所収の秀才申文三篇は実作か |
慶応義塾大学:佐藤道生 |
| ■第32回大会 平成25年(2013年) |
於 早稲田大学 |
| 9月28日(公開講演会)日本近代文学と中国 |
|
| 芥川龍之介「杜子春」と唐代伝奇「杜子春伝」とのあいだ―中国文学の角度からの確認事項いくつか― | 茨城大学教授:増子和男 |
| 谷崎潤一郎にとっての中国―「萎喰う虫」に描かれた上海を中心に― | 早稲田大学非常勤講師:宮内淳子 |
| 若き荷風と中国―『上海紀行』などを中心に― | 東華大学准教授:銭暁波 |
|
9月29日(研究発表) |
|
| 陳曼寿『日本同人詩選』について | 成蹊大学(研):日野俊彦 |
| 白川琴水著『本朝彤史列女伝』について―『大日本史』列女伝との比較を中心に― | 京都女子大学(非):森岡ゆかり |
| 『太平記』における『白氏文集』摂取と反映―旧紗本系から刊本系へ― | 明治大学(院):金木利憲 |
| 藤原頼長と告文―『台記』所載の告文をめぐって― | 早稲田大学(院):柳川響 |
| 大江匡衡の漢詩文に見える潘岳像 | 早稲田大学(院):呂天雯 |
| 大江千里の和歌序と源氏物語 | 京都大学(院):山本真由子 |
| 催馬楽「浅緑」小考―漢詩における君主賛美との関わりから― | 同志社大学(院):松沢佳菜 |
| 延喜元年の菅原道真 | 筑波大学:谷口孝介 |
| ■第33回大会 平成26年(2014年) |
群馬県立女子大学 |
| 9月20日(公開講演会) |
|
| 唐土の美女と源氏物語の女性達 | 京都女子大学教授:新間一美 |
| 江戸時代における風景詩の変貌 | 成蹊大学教授:揖斐高 |
|
9月21日(研究発表) |
|
| 隠棲後の兼明親王の文学―孤高と閑適― | 東京大学(院):宋晗 |
| 空海書簡に見る書儀表現の受容 | 信州大学:西一夫 |
| 和漢聯句における白詩の受容 | 武蔵野大学:楊昆鵬 |
| 菅原道真の漢詩文に見られる『荘子』の受容―「優遊」と「涯岸」をめぐって― | 京都女子大学(院):李現 |
| 『菅家文草』巻二「晩秋二十詠」の表現と詩興 | 宮崎大学:中村佳文 |
| 駅楼での思い―『源氏物語』須磨の巻「駅の長にくしとらする人」をめぐって― | 筑波大学:谷口孝介 |
| 旅する詩人の肖像―俳諧における驢馬の表現をめぐって― | 関西大学(院):中村真理 |
| 夏目漱石と〈蒙求〉 | 国文学研究資料館(総合研究大学院大学):相田満 |
| ■第34回大会 平成27年(2015年) |
関西大学 |
|
9月12日 公開シンポジウム「和漢をつなぐ楽とことば」 |
|
|
多様なる遣唐楽人の姿 ―階層・地域・ブックロード― |
ノートルダム清心女子大学准教授:原豊二 |
| 敦煌歌辞と日本を結ぶもの | 関西大学教授:長谷部剛 |
| 詞の平仄からみた敦煌音楽の復元 | 一橋大学(非):橘千早 |
|
9月13日(研究発表) |
|
|
○菅原道真「奉謝平右軍」詩考 ―負けわざとしての「侯圭新賦」― |
大東文化大学(院):馮芒 |
| ○『源氏物語』帚木三帖における「うつせみ」と『蜻蛉日記』―『菅家文草』『新撰万葉集』にみえる蟬と人との関わり― | 京都女子大学(院・研修者):朝日眞美子 |
| ○『元亨釈書』「資治表」に見える春秋学の受容 | 中国人民大学(院):胡照汀 |
|
○『杜家立成雑書要略』の書儀的性格 ―文体・表現・受容の観点から― |
信州大学:西一夫 |
| ○『竹取物語』を読みなおす―平安前期文人層における〈神仙ワールド〉の復元的共有― | 信州大学(名):渡辺秀夫 |
| ○荻生徂徠『絶句解』における読法 | ノートルダム清心女子大学:小野泰央 |
| ○古文辞派の〈個性〉 | 上智大学:福井辰彦 |
| ■第35回大会 平成28年(2016年) |
成城大学 |
|
9月24日 公開講演会 |
|
| 音と空間の和漢比較文学 | 京都大学教授:大谷雅夫 |
| 源氏物語の時代の男性の文学―『本朝麗藻』再読― | 金沢学院大学教授:柳澤良一 |
|
9月25日(研究発表) |
|
| ○『今昔物語集』巻九所載の羊転生譚の特徴と位置づけについて | 早稲田大学(院):趙倩倩 |
| ○故宮博物院本『蒙求』77・78「賀脩儒崇孫綽才冠」の諸問題 | 岐阜女子大学:岡部明日香 |
| ○和漢聯句における政治性―後陽成院晩年の作品を中心に― | 武蔵野大学:楊昆鵬 |
| ○『近世佳人伝』「花扇伝」に見られる蒲生重章の創作態度 | 早稲田大学(院):長田和也 |
| ○近世俳諧と妖狐伝―白詩受容に注目して― | 群馬県立女子大学:安保博史 |
| ○儒者と縁起―「園城寺龍華会縁記」を中心にして― | 小山工業高等専門学校:山﨑明 |
| ○勅撰三漢詩集および『懐風藻』の序文探求―唐代総集の序文と対照して考察する― | 函館大学付属柏稜高等学校:半谷芳文 |
| ○『源氏物語』大君の形象と漢詩文表現 | 國學院大學(兼):笹川勲 |
| ○大江匡衡「八月十五夜於江州野亭言志」試論―都と辺土― | 東京大学(院):宋晗 |
| 藤原有国伝の再検討 | 慶應義塾大学:佐藤道生 |
| ■第36回大会 平成29年(2017年) |
大手前大学 |
|
9月30日(土) 公開シンポジウム 「和漢聯句への招待」 |
|
| 第一部 講演 |
|
| 司会 | 神戸学院大学:中村健司 |
| ○連歌から和漢聯句へ | 熊本大学准教授:竹島一希 |
| ○戦国大名の文芸と和漢聯句 | 慶應義塾大学教授:小川剛生 |
| 第二部 公開輪読「和漢聯句を読む」 | |
| 司会 | 武蔵野大学:楊昆鵬 |
| 発表者 | 京都大学:河村瑛子 |
| 発表者 | 同志社大学:大山和哉 |
| 発表者 | 慶應義塾大学(院):川﨑美穏 |
| コメンテーター | 京都大学(名):大谷雅夫 |
| コメンテーター | 和光大学:深沢眞二 |
| コメンテーター | 京都大学:長谷川千尋 |
|
10月1日(日)(研究発表) |
|
| ○『懐風藻』「人物伝」と誄 | 京都府立大学(院):川上萌実 |
| ○都良香に見る詩文兼作意識の芽生え | 東京大学(院):宋晗 |
| ○其角の漢籍受容―「嘲仏骨表」を中心に― | 関西大学(院):三原尚子 |
| ○明治中期の「天譴論」―国分青厓「恩沢渥」を通して― | 早稲田大学(院):松葉友惟 |
| ○正岡子規が読んだ江戸漢詩詞華集―『才子必誦 崑山片玉』・『日本名家詩選』― | 慶應義塾大学:合山林太郎 |
| ○宇都宮遯庵の詩文と『錦繍段』注釈 | 中央大学:小野泰央 |
| ○大江千里『句題和歌』述懐部の創設について | 佛教大学(非):三宅えり |
| ○大江朝綱と「菅秀才」との交流―朝綱、晩年の一齣― | 早稲田大学(院):川村卓也 |
| ○源氏物語の巻名と漢詩文―「桐壺」「帚木」など― | 関西学院大学(非):新間一美 |
| ■第37回大会 平成30年(2018年) |
帝塚山学院大学 |
|
9月22日(土) 公開討論会 「近世・近代の書画を読む」 |
|
| コーディネーター | 早稲田大学:池澤一郎 |
| パネリスト | 慶應義塾大学:堀川貴司 |
| パネリスト | 上智大学:長尾直茂 |
| パネリスト | 帝塚山学院大学:福島理子 |
|
9月23日(日)(研究発表) |
|
| ○江湖詩社社友の詩文に見る「窮者而後工」の受容 | 早稲田大学(院):藤冨史花 |
| ○近世東アジア女性詩人としての原采蘋─鮑之蕙(清)と金錦園(朝鮮)の紀行詩と比較して─ | 早稲田大学(院):柯明 |
| ○祇園南海編『鏡花水月集』について | 中央大学:小野泰央 |
| ○太宰治「竹青―新曲聊斎志異―」の作意―原典『聊斎志異』との比較考察を通じて― | 大阪大学(院):陳潮涯 |
| ○玉藻前と照魔鏡―『絵本三国妖婦伝』と『画本玉藻譚』における「狐妖退治」の形成をめぐって | 馮超鴻 |
| ○「申執政人」という方法―三善道統と大江匡衡― | 筑波大学(院):出口誠 |
| ○『杜家立成雑書要略』の臥病関連文例の特質 | 信州大学:西一夫 |
| ■第38回大会 令和元年(2019年) |
上智大学 |
|
10月5日(土) 公開シンポジウム「日本文学のなかの白話小説・再考」 |
|
| コーディネーター | 就実大学:丸井貴史 |
| パネリスト | 日本学術振興会特別研究員:宮本陽佳 |
| パネリスト | 神田外語大学:及川茜 |
| パネリスト | 東北学院大学:金永昊 |
|
10月6日(日)(研究発表) |
|
| ○日本書紀における語りの一方法―由来を示す「縁也」の表現形式をめぐって― | 日本学術振興会特別研究員(PD):葛西太一 |
| ○『萬葉集』柿本人麻呂「吉野讃歌」における漢籍の受容―南朝宋の鮑照「侍宴覆舟山二首」との比較を通して― | 京都府立大学(院):内田夫美 |
| ○一条朝の「聖代」―起家による「申官爵」奏状を中心に― | 筑波大学(院):出口誠 |
| ○平安後期の藤原摂関家における辞表の在り方について | 早稲田大学(院):川村卓也 |
| ○亀井昭陽『傷逝録』と広瀬父子の哀悼詩について―淡窓の連作六首「読昭陽先生傷逝録」を中心に― | 早稲田大学(院):藤冨史花 |
| ○近世における予譲評価の変容について | 長崎大学:中島貴奈 |
| ○近世近代における漢文直読(中国語音読)の挫折について | 早稲田大学:池澤一郎 |
| ■第39回大会 令和2年(2020年) |
オンライン開催 |
| 講演会(内容は『和漢比較文学』第66号に掲載予定) |
|
| 幕末・明治期の会津・福島と漢文学―歴史資料としての漢詩文の意義― | 慶應義塾大学准教授:合山林太郎(司会) |
| 広沢安任と幕末明治―漢文史料を中心として― | 東京経済大学史料室嘱託:友田昌宏 |
| 南摩羽峰の幕末維新と孝明天皇宸翰問題 | 実践女子大学短期大学部名誉教授:小林修 |
研究発表(10月5日(月)~10月15日(木)を期間として、「発表原稿・資料等」と「質疑応答」をホームページ上に掲載) |
|
| ○『新撰万葉集』「蕭郎」考 | 早稲田大学(院): 倪晨 |
| ○大江匡房『江都督納言願文集』における「竜女」 | 筑波大学(院):金澤真美 |
| ○霊地の起源伝承における「毒龍」の概念―『江島縁起』『筥根山縁起』を中心として― | 早稲田大学(院):田中亜美 |
| ○林羅山の学問における〈模擬〉 | 中央大学:小野泰央 |
| ○森川許六『和訓三体詩』の「詩意」の手法 | 上智大学(院):砂田歩 |
| ○漢文学の影響と俳諧性(見立)から見た与謝蕪村の発句の特徴 | 苫小牧駒澤大学:山口莉慧 |
| ○広瀬旭荘における詠史 | 早稲田大学(院):森隆夫 |
| ○会津磐梯山噴火と新聞文芸――新聞漢詩と新聞小説―― | 早稲田大学(院):松葉友惟 |
| ○暗喩としての日輪と虹と雲―韋軒・弘毅斎・羽峰の漢詩唱和― | 早稲田大学:池澤一郎 |
| ■第41回大会 令和3年(2021年) |
オンライン開催(開催協力校 早稲田大学) |
|
10月2日(土) シンポジウム「廣瀬淡窓・旭荘とその門流」 |
|
| 漢詩文に見る廣瀬淡窓の人間愛の深さと教育への情熱 | 早稲田大学:池澤一郎 |
| 廣瀬旭荘の詩と書画 | 帝塚山学院大学:福島理子 |
| 廣瀬旭荘の塾運営と門下生 | 日田市咸宜園研究教育センター:溝田直己 |
|
10月3日(日)(研究発表) |
|
| ○卜を得意とする扁鵲―『注好選』を中心に― | 早稲田大学(院):伊 丹 |
| ○文人画家亀井少琴の画業―慶応義塾大学斯道文庫所蔵「少琴詩雑記」調査を軸に― | 清泉女子大学(非):黒川桃子 |
| ○大沼枕山による広瀬旭荘批判 | 早稲田大学(院):森隆夫 |
| ○原古処の「読源語 五十四首」における語義の二重性について―日本漢詩における「掛詞」― | 早稲田大学(院):柯 明 |
| ○園南海作新井白石六十寿賀詩について | 慶應義塾大学附属斯道文庫:堀川貴司 |
| ○法隆寺薬師如来光背銘考続貂―「仕奉」に注目して― | 筑波大学:谷口孝介 | ■第42回大会 令和4年(2022年) |
オンライン開催(開催協力校 フェリス女学院大学・宋晗研究室) |
|
9月24日(土) シンポジウム「訓読という行為―解釈・翻訳として―」 |
|
| 開催趣旨説明 | 筑波大学:谷口孝介 |
| 基調講演:訓読の力 | 京都大学名誉教授:木田章義 |
| 報告1 『日本書紀』の訓読がもたらしたもの | 武蔵大学:福田武史 |
| 報告2 国語教育の立場から訓読の学びを位置づける | 信州大学:西 一夫 |
|
9月25日(日)(研究発表) |
|
| ○古今集時代の〈月下の白菊〉の構図形成について | 大阪大学(研):蒲 姣艶 |
| ○源氏物語における朧月夜の人物造型 ― 韓朋譚の関わりについて ― | 佛教大学(非):今井友子 |
| ○詩歌合における漢詩句の詠法─『元久詩歌合』と『内裏詩歌合』を中心に─ | 大阪大学(院) 黄 夢鴿 |
| ○人工知能と人間詩人による共同作詩の試み―AI「中太郎」の和歌に対する石倉秀樹氏の漢詩翻案 | 西安交通大学 金 中 |
| ○幸徳秋水「鳥語傳」について | 京都大学(名) 金 文京 |
| ■第43回大会 令和5年(2023年) |
京都府立大学(ハイブリッド開催) |
|
10月7日(土) シンポジウム「儒者とは何か、文人とは何か」 |
|
| 開催趣旨説明・司会 | 慶應義塾大学:合山林太郎 |
| 報告1 文人という人間類型の射程 | フェリス女学院大学:宋 晗 |
|
報告2 李白はなぜ江戸時代に人気が出たのか? ―近世儒者の自己像から考える― |
国文学研究資料館:山本嘉孝 |
| ディスカッサント | 神戸市外国語大学:紺野達也 |
| ディスカッサント | 宮内庁書陵部:鈴木蒼 |
| ディスカッサント | 東京大学:高山大毅 | ディスカッサント |
コロンビア大学:袁葉 (Yuan Ye) |
|
10月8日(日)(研究発表) |
|
|
○幽人を訪ねる ─嵯峨天皇の「訪幽人遺跡」詩における幽人像を凝視する |
早稲田大学: クリストファー・リーブズ |
| ○『田氏家集』元慶五年作における閑適詩の受容について |
筑波大学(院修了): 根岸賢太郎 |
| ○「瘴」考―日本古代・中世の「瘴病」と「瘴意識」 | 京都大学(院) 黄 弋粟 |
| ○梁川星巌『西征詩』の諸本と表現 | 上智大学 福井辰彦 |
| ○次韻応酬による時事漢詩―広瀬旭荘と奥野小山の例― | 早稲田大学(院):森 隆夫 |
| ○会津藩士南摩羽峯の長篇七古「無題」について | 早稲田大学:池澤一郎 |